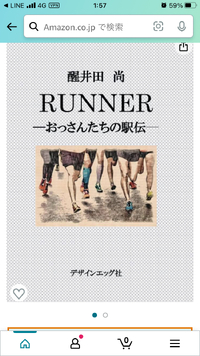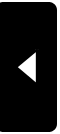2015年01月31日20:06


写真は、 邑瀬三男さん撮影。
原田橋落橋現場。≫


写真は、 邑瀬三男さん撮影。
この記事へのコメント
凄い状況ですね。写真ありがとうございます。横倒しになって落橋しているのが原田橋でしょうか。作業員の方の状況が心配です。
Posted by Kuni at 2015年01月31日 20:19
橋の崩落に巻き込まれた方がいらっしゃるとか。最悪な結果にならぬようお祈りいたします。
ちょうど先週の日曜日、ここを通ったのですが、新しい橋も急な崖の直下に造られていて、地盤が不安定に見えます。せめて少し南、佐久間高校の北縁に沿って造るべきだったかもしれません。
ちょうど先週の日曜日、ここを通ったのですが、新しい橋も急な崖の直下に造られていて、地盤が不安定に見えます。せめて少し南、佐久間高校の北縁に沿って造るべきだったかもしれません。
Posted by 佐久間が好きです at 2015年01月31日 20:32
生活道路なのに着工は遅いし、地元では「どうして橋脚を使用しない吊り橋?。30m長い橋を架ければ崖を回避できるのに?。」といった声ばかりでした。こんな大惨事になっても、国は責任を押し付けあいメンツにこだわって、同じような場所に橋脚を全く使用しない吊り橋をつくるのでしょうか。時間が戻って欲しいです。
Posted by いきどおり at 2015年01月31日 21:02
小石の落石を理由に通行止めにするには、相当な勇気と行動力が必要ですが、判断をしたのは亡くなった市役所職員の二人でしょうか。心から敬意を表します。
3年前の行政が主催した地元住民への説明会で橋の老朽化を、天竜川に橋脚を作って橋を支えて欲しいといった意見も出された気がしますが、簡単に重量車両の規制で片付けた行政。あまりにも悲しすぎます。
3年前の行政が主催した地元住民への説明会で橋の老朽化を、天竜川に橋脚を作って橋を支えて欲しいといった意見も出された気がしますが、簡単に重量車両の規制で片付けた行政。あまりにも悲しすぎます。
Posted by 悲しすぎます at 2015年01月31日 21:50
いきどおりさん、下流側に作られてる新しい橋は吊り橋ではなく橋脚を使った橋です。
橋が落橋する以前に何度か見ているので間違いないです。
橋が落橋する以前に何度か見ているので間違いないです。
Posted by 通りすがり at 2015年01月31日 21:55
悲しすぎますさん
行政の対応が遅いとか通行規制だけの対応とか言われてますが、現実問題として生活道路である現場の橋を完全に通行止めにすると迂回路が全くない(70km迂回は現実的でない)為通行規制は新橋が出来るまでの苦肉の策だった様にも思えます。
行政の対応が遅いとか通行規制だけの対応とか言われてますが、現実問題として生活道路である現場の橋を完全に通行止めにすると迂回路が全くない(70km迂回は現実的でない)為通行規制は新橋が出来るまでの苦肉の策だった様にも思えます。
Posted by 通りすがり at 2015年01月31日 22:07
通りすがりさん、橋脚に見えたのは橋桁架設の為の、鋼製支保工ですので、架設後は取り外します。
Posted by 危険個所にどうして... at 2015年01月31日 22:10
下流側に架けられている新しい橋は吊り橋でもなく、橋脚を使った橋でもありません。橋を架ける過程で橋脚の様な物で受けていますが完成したらアーチで持たせる構造なので橋が完成したら橋脚の様な物は全てなくなりますよ。
Posted by 原田橋 at 2015年01月31日 22:21
情報が少ない中での投稿は控えた方がいいのかもしれませんが、通行止めの措置をしなければ、一般車両が巻き込まれた恐れがあったような気がします。1年前も警備員の制止を無視して2人乗りの重量オーバーの車両が川に転落して死亡した事故がありました。小石が落ちたと通報した現場会社も危機管理が徹底しているし、、迷わず通行止めにした市役所もすごい判断だと思います。特に1週間前の佐久間駅伝の選手がいちばん通過している時にこの状況になったらと思うと、強くこの思いは感じます。
Posted by 悲しすぎます at 2015年01月31日 22:56
橋の中間に橋脚を立てないのは、豪雨等による河川の増水時に流路を阻害するため、河川管理者がそれを認めてくれないからだと思います。工事用の仮設橋脚(ベントと呼びます)は渇水期(流量が少ない時期)に限り設置が認められ、その間に橋桁をかける工事をしなければなりません。
今回の落橋の原因は写真を見る限り、桁を吊るケーブルを固定するためのアンカレイジと呼ばれる部分の岩盤斜面が崩壊したからと考えられます(これにより桁を支えるものがなくなった)。
一方、現在建設中の新橋は桁本体だけで荷重を支えるアーチ橋で設計されていることから(//img02.hamazo.tv/usr/p/u/p/puppu/2013-03-24s%E6%96%B0%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%A9%8B%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%94%BB_1.jpg )、新しい橋では同じ事故が起こる可能性はありません。今の橋梁建設技術では吊り橋構造でなくてもより長い橋桁をかけられるようになっています。
今回の落橋の原因は写真を見る限り、桁を吊るケーブルを固定するためのアンカレイジと呼ばれる部分の岩盤斜面が崩壊したからと考えられます(これにより桁を支えるものがなくなった)。
一方、現在建設中の新橋は桁本体だけで荷重を支えるアーチ橋で設計されていることから(//img02.hamazo.tv/usr/p/u/p/puppu/2013-03-24s%E6%96%B0%E5%8E%9F%E7%94%B0%E6%A9%8B%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%94%BB_1.jpg )、新しい橋では同じ事故が起こる可能性はありません。今の橋梁建設技術では吊り橋構造でなくてもより長い橋桁をかけられるようになっています。
Posted by 名無し at 2015年01月31日 23:22
お二人の尊い命が、、、。
ご冥福をお祈りします。
この場所は、魔の絶壁。命がけで通過する危険個所でした。
新橋建設説明会のときも、「なぜここへ?」という声が大勢を占めました。
地元の人たちの声に聞く耳を持たなかった行政が招いた惨事です。
予算というのを楯に、人の命を軽んじた結果がこれ。
もう少し、思いやりのある判断ができなかったものかと、残念でなりません。
ご冥福をお祈りします。
この場所は、魔の絶壁。命がけで通過する危険個所でした。
新橋建設説明会のときも、「なぜここへ?」という声が大勢を占めました。
地元の人たちの声に聞く耳を持たなかった行政が招いた惨事です。
予算というのを楯に、人の命を軽んじた結果がこれ。
もう少し、思いやりのある判断ができなかったものかと、残念でなりません。
Posted by 大千瀬っ子 at 2015年01月31日 23:27
at 2015年01月31日 23:27
 at 2015年01月31日 23:27
at 2015年01月31日 23:27 3年前に橋の老朽化が問題になった時、つり橋と崖とを結ぶロープを強固にして8トン以下の車両の安全を確保したように思います。
新しい橋は工事予算の安い(?)早期完成の橋脚の橋で十分だったと思っているせいか、3年前の原田橋の補強は、ロープの補強と併せて原田橋を支える橋脚を2か所設置していれば、崩土があっても下から支える力で橋の崩壊は免れたかもしれないと少し思います(素人考えですが)。
管理人さんが11月29日に掲載してくれた三遠南信の平沢ICまでの工事が先行して加速してもらいたいです。
新しい橋は工事予算の安い(?)早期完成の橋脚の橋で十分だったと思っているせいか、3年前の原田橋の補強は、ロープの補強と併せて原田橋を支える橋脚を2か所設置していれば、崩土があっても下から支える力で橋の崩壊は免れたかもしれないと少し思います(素人考えですが)。
管理人さんが11月29日に掲載してくれた三遠南信の平沢ICまでの工事が先行して加速してもらいたいです。
Posted by 悲しすぎます at 2015年01月31日 23:51
現在位置より下流に新橋を架けると橋長が長くなりカネがかかるという理由だけで危険な現在位置に地元の反対を押し切ってごり押しで建設中だったようですがバチが当たったとしか言いいようがない。
新橋の橋台工事の影響で背後の地山の足許が緩んだために崩落したのではないだろうか。
あらかじめ地山補強土工(アンカーやロックボルト)を施しておくべきでした。
行政の責任者はクビだね。
新橋の橋台工事の影響で背後の地山の足許が緩んだために崩落したのではないだろうか。
あらかじめ地山補強土工(アンカーやロックボルト)を施しておくべきでした。
行政の責任者はクビだね。
Posted by 土方のオヤジ at 2015年02月01日 00:14
中央構造線の破砕帯の峡谷に沿った所なので
今となっては皆さまの、たられば論が虚しくなります…
画像を提供された方ありがとうございます
NHKニュースでも見ましたが
改めて
今回の災害事故で亡くなられた
お二人の浜松市担当者様のご冥福をお祈りします。
今となっては皆さまの、たられば論が虚しくなります…
画像を提供された方ありがとうございます
NHKニュースでも見ましたが
改めて
今回の災害事故で亡くなられた
お二人の浜松市担当者様のご冥福をお祈りします。
Posted by 近江人 at 2015年02月01日 00:34
現在の位置に新橋建設を決定された市の上層部の方には判断ミスとして反省して頂きたいと思います。
Posted by 大変です at 2015年02月02日 22:18
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。